読み聞かせは、親子のあたたかい時間を紡ぐ大切な営みです。
ただ、意図せぬ「やってはいけないこと」が、世界を壊してしまうこともあります。
この記事では、読み聞かせでやってはいけない「4つのNG」を中心に、子どもの集中力や想像力を守る読み方を提案します。
読み聞かせを始める前に知っておきたいこと
読み聞かせを始める前に意識しておきたいことは、「準備」と「心構え」です。
子どもたちの心と脳に届く読み方は、読み始める前の条件が整ってこそ生きるものだからです。
子どもの脳と心に届く「自然なスピード」
子どもの脳と心に響かせたいなら、ゆっくり過ぎる読み方は避けたいですね。
特に幼児期は、右脳が優位でイメージや感覚が鋭い時期とされます。
ゆっくり過ぎると聞き手が退屈し、物語世界から離れてしまうこともあります。
自然な会話のスピードで、適度なリズムをもたせて読み進めることが、集中力を支える工夫になります。
環境づくり:静かさと安心感を大切に
読み聞かせはコンテキストが大事です。
周囲の音、照明、子どもの体勢…これらが雑だと集中を妨げてしまいます。
静かな空間、照明の落ち着き、子どもが安心できる姿勢を用意しておきましょう。
始める前に「読むよ」の合図をお互いに確認するのも、安心感につながります。
絵本の選び方:対象年齢より「興味」を基準に
絵本選びで年齢にこだわりすぎると、子どもが食いつかないことがあります。
もっと大切なのは、その子が「読みたい」と感じるかどうかという興味基点です。
絵の魅力、物語の展開、文字の量、触感、テーマなどを観察して選びましょう。
興味を持てる題材なら、最後まで楽しんで読めることが多くなります。
読み手の心構え:親もリラックスして楽しむ
読み手自身が緊張していると、声も身体も硬くなります。
親が「うまく読まなきゃ」と意気込むと、読み方がぎこちなくなる場合もあります。
まず親自身が絵本時間を楽しむことを意識しましょう。
子どもはその空気を感じ取りますから、リラックスした声と表情で読み始めることが鍵です。
※合わせて読みたい「絵本の読み聞かせ いつから始める?」
読み聞かせで避けたい4つのNG行動
読み聞かせ中に、ついやってしまいがちな「やってはいけない行動」があります。
これらのNGを知ることで、子供の集中力を守り、物語世界を壊さない配慮をしましょう。
以下では4つの典型的な誤りと、それを回避するヒントを紹介します。
わざとゆっくり読みすぎてしまう
ゆっくりゆっくり読みすぎると、子どもたちの集中力が途切れがちになります。
物語テンポが鈍く感じられて、「退屈かも」と思われてしまうこともあります。
理解度を気にしてゆったり読みたくなる気持ちはわかりますが、それが逆効果になりかねません。
物語の起伏や展開を意識して、適度なスピードで読み切ることを心がけましょう。
声色を大げさに変えてしまう
登場人物のセリフや場面で、つい声を大げさに変えてしまうことがあります。
しかし強すぎる演技的な抑揚は、子どもの想像力を奪ってしまうかもしれません。
大人としては感情を込めたいけれど、演技しすぎは逆効果になることもあります。
基調は安定した声で、必要最小限の変化にとどめるのが望ましいでしょう。
絵やリズムを無視して淡々と読む
絵本の醍醐味は、絵・リズム・言葉が一体となって世界をつくることです。
淡々と文字を追うだけでは、それらの要素の輝きが失われます。
リズムが刻まれた表現、繰り返し、音の響きなどに注意を払いながら読む工夫が必要です。
絵を指し示したり、少し余韻をもたせたりする手触りも、大きな効果を生みます。
読み終えたあとにほめ言葉を忘れる
読み終わった瞬間に、つい次の準備に気をとられて、ほめる行為を忘れてしまうことがあります。
ほめ言葉は子どもの自己肯定感を促す大切な要素です。
「よく聞いてたね」「最後まで一緒に来れたね」など、短いひとことでも十分価値があります。
読み終えてすぐに肯定的な言葉を伝えることで、次につながる読書体験になります。
読み聞かせ後に育つ親子の自己肯定感
読み聞かせが終わったあと、その余韻と対話で親子の自己肯定感を育める時間になります。
子どもに「認められた」と感じさせる言葉かけ、親自身の心のあり方、再読を促す関係性がここで問われます。
「よく聞いていたね」と一言で十分なほめ方
読み終わった後、子どもを過度に褒める必要はありません。
「よく聞いていたね」という一言は、それだけで子どもにとって重みがあります。
量よりも真意が大切です。
心からの言葉を、タイミングよく伝えることで、子どもの「認められた」という感覚を育てられます。
無理にほめず、行動を肯定する工夫
感情を過剰に表現するほめ言葉は、逆に子どもを萎縮させてしまうこともあります。
無理に「すごい!」「天才!」と連発せず、子どもの行為そのものを肯定する形にするのがコツです。
「最後まで読めてよかったね」「本を大事に扱ってえらいね」というような表現がいいですね。
行動や姿勢を肯定する形で伝えると、子どもたちの自己肯定感は静かに強まります。
親自身の自己肯定感も育つ読み聞かせ
読み聞かせは子どものためだけでなく、親自身にとっても自己肯定感を育てる時間になります。
「今日はひと息ついて、子どもとこの時間を持てた」という感謝の気持ちを内側で味わってみてください。
親が自分を認める余裕が増えると、その安心感が子どもに伝わります。
親子ともに成長する相互的な営み、それが読み聞かせの深みでもあります。
「また読んでね」と言われる関係をつくる
読み聞かせを重ねていくうちに、子どもから「また読んでね」と言ってもらいたいですよね。
そのためには、終わった直後だけでなく、翌日以降に余韻を思い出させる問いかけも有効です。
「昨日のお話、どこが好きだった?」と自然な会話を誘うこともいいでしょう。
こうした積み重ねが、親子の本への愛着と関係をじわじわ育ててくれます。
毎日の習慣にするためのアイデア
読み聞かせを毎日の習慣にするには、無理なく続けられる工夫が鍵です。
ここでは、短時間実践法、段階的ステップ、苦手克服、家族参加のアイデアをお話しますね。
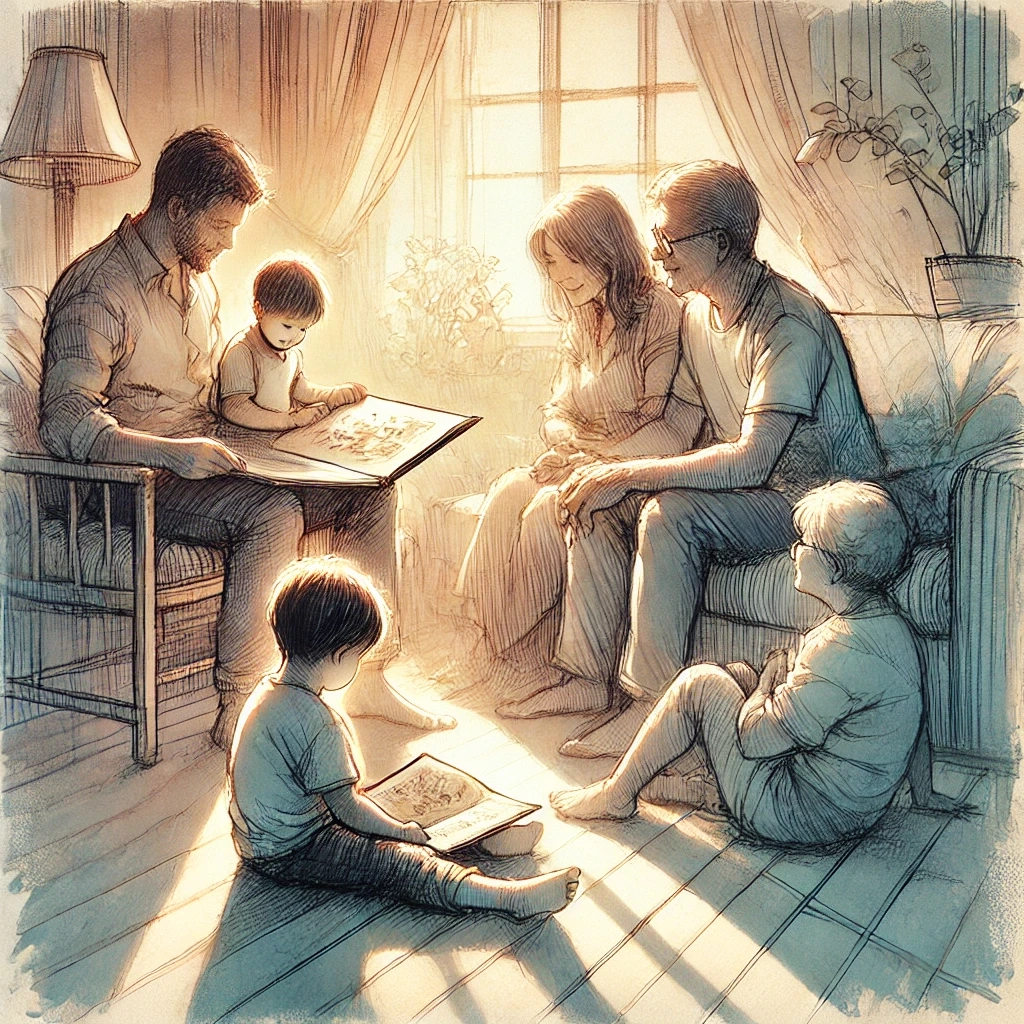
5分でもOK、スキマ時間で取り入れる
毎日続けるには無理しないことが肝要です。
5分だけでも、子どもと一緒にページをめくる時間を持つだけで、読み聞かせは効果を発揮します。
「寝る前」「朝」「お風呂後」などスケジュールの隙間に組み込む工夫をしてみてください。
短時間でも継続することが、集中力・言葉・想像力の育成につながります。
赤ちゃん絵本から始めてステップアップ
文字の量を増やす前に、まずは赤ちゃん絵本や言葉少ないものから始めるのがよいでしょう。
ストーリー性よりも絵の豊かさ、リズム、余白を味わえる作品が適しています。
徐々に文章量の増える作品にステップアップしていくことで、子どもの理解力を育てつつ興味をつなげられます。
段差を小さくするように進めていくことが、子どもの負担を減らすコツです。
読み聞かせが苦手な場合のシンプルな工夫
読み聞かせが苦手だからと遠ざけてしまうと、習慣化が崩れてしまうかもしれません。
まずは絵のみを見せながら語りかける方法でも十分価値があります。
「今日はこれを一緒に見るね」と軽く始めてみるのも手です。
気負わず、完璧を求めず、楽しむことを最優先にする習慣化の工夫を試してみましょう。
家族で分担して楽しむ読み聞かせ
読み聞かせを「親だけ」の仕事にしないことも、長く続ける秘訣です。
夫婦で代わりばんこに読む、祖父母や兄弟と交代で読むなど、家族で関わることで楽しくなります。
異なる声と表現が混ざると、子どもにとって多様な経験になります。
家族みんなの協力で、読み聞かせを日常の風景にしていきましょう。
まとめ
読み聞かせは、単なる読み方だけでなく、準備、表現、余韻、習慣化の全体で質が決まります。
やってはいけないNGを知ることで、集中力と想像力を守れる読み方が見えてくるでしょう。
親も子も、自分自身を大切にしながら、絵本時間を育てていきましょう。
本記事を参考に、あなたの読み聞かせが、親子の宝物に育つことを願っています。
※合わせて読みたい「絵本の読み聞かせ いつから始める?」
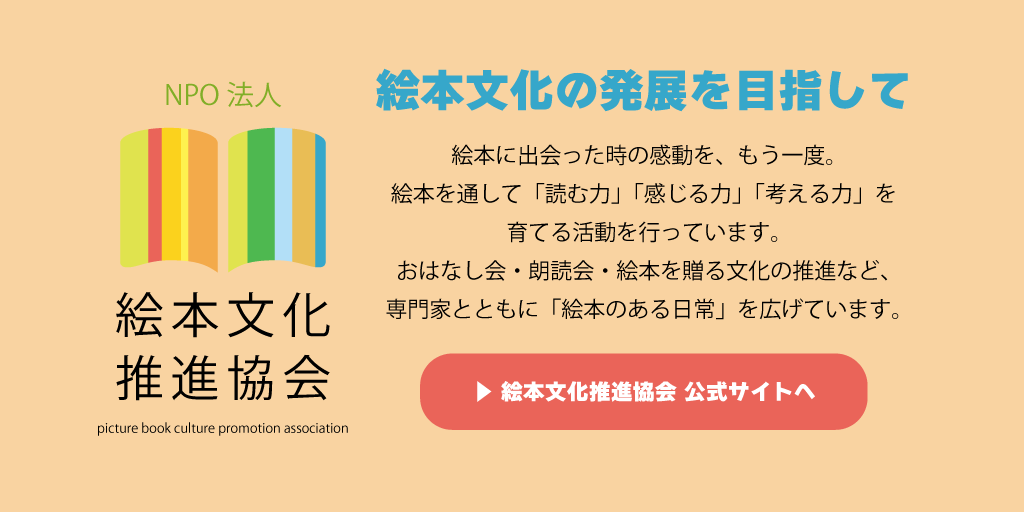
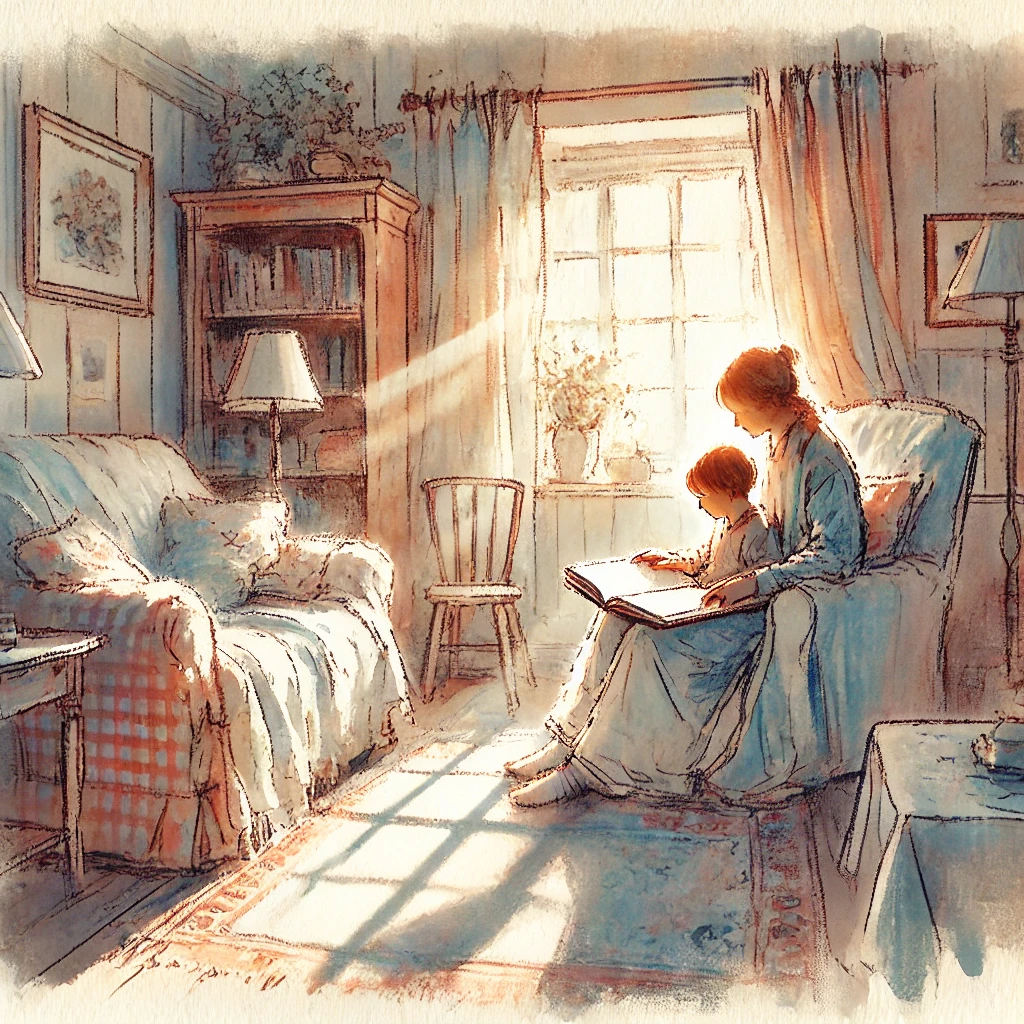


コメント